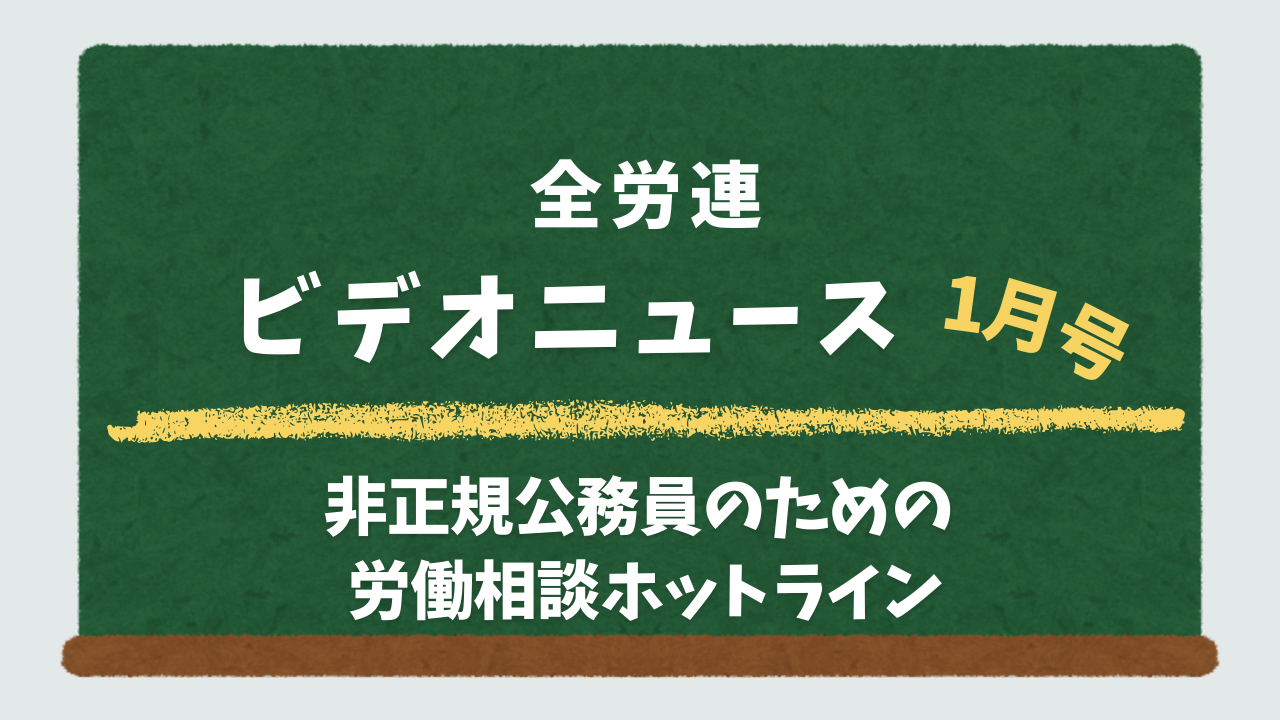知ってるようで知らない?労働委員会を活用しよう
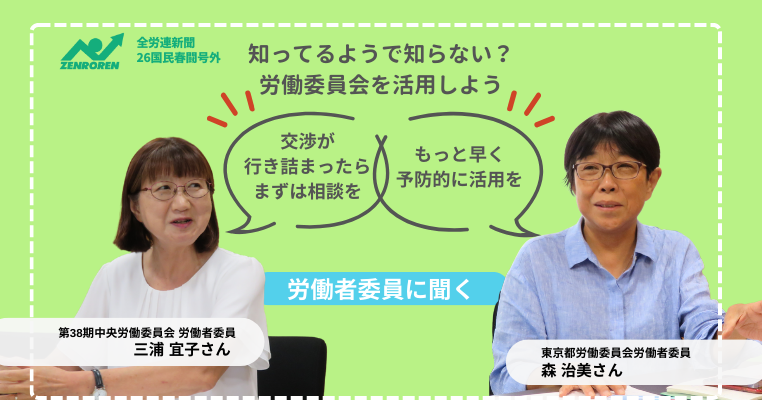
紙面対談
第38期中央労働委員会(中労委)労働者委員 三浦 宜子さん
東京都労働委員会(都労委)労働者委員 森 治美さん
労働組合の団体交渉権強化へ
25国民春闘で全労連はたたかう労働組合のバージョンアップを掲げて要求実現を迫り、要求提出組合の83・1%が有額回答を引き出した。一方で、額では物価高騰を上回る大幅賃上げには届いていない。労働委員会の労働者委員として最前線で活躍する三浦宜子さん(中労委)と森治美さん(都労委)に本格化する秋季年末闘争や来春闘で要求を前進させるための労働委員会の活用について話を聞いた。
労働者の団結を擁護する制度-労働委員会でできること
労働委員会とは
労働者が団結することを擁護し、労働関係の公正な調整を図ることを目的として、労働組合法にもとづいて以下の通り設置される。
【1】中央労働委員会(国の機関)
【2】都道府県労働委員会(都道府県の機関)
委員会は、労働者委員、使用者委員、公益委員の3者で構成される。
労働委員会の機能
【1】労働争議の調整(あっせん、調停及び仲裁)
【2】不当労働行為の審査
【3】労働組合の資格審査、個別労働紛争解決のあっせんも行う(44道府県労委)
三浦 憲法28条は、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を労働基本権として保障しています。労働委員会(以下委員会)は、労働者の団結を擁護し、労使関係の公正な調整を図るために、労働組合法に基づいて設置された機関です。
森 職場では人権が守られていないことが多く、施設管理権を持ち出してビラ配布を禁止する、就業規則に組合活動禁止と書くなど、違法な例は少なくありません。悩んで足が止まったり、多くが「もうどうにもならない」状況になってから労働委員会に持ち込まれるのですが、本来はもっと早く、予防的に活用してほしい制度です。
三浦 交渉が壁にぶつかったとき、救済申立てだけでなく、あっせん・調停・仲裁といった調整機能を使うこともできます。あっせんは、不当労働行為の救済申立てに比べれば、短時間で手続きも簡単です。双方が受諾しないと成立しませんが、第三者機関が介入することで、行き詰まりが解消される場合もあります。委員会事務局に相談すれば申請準備の段階から助言を受けられます。まずは相談から始め、制度を活用することが重要です。
森 労組法7条には「不利益取扱い」「団交拒否」「支配介入」の禁止が明記されています。
団体交渉における不誠実な対応の具体例を紹介すると、回答の引き延ばし、経営資料提出の拒否、同じ回答の繰り返し、あるいは「デッドロック(「これ以上同じ、話しても無理」)を理由に交渉を打ち切ることなどがあります。団体交渉の目的は合意をめざし協定を結ぶことです。合意を結ぶために双方の努力が必要にもかかわらず、これらは団交拒否をしているのも同然で、不当労働行為に当たります。
三浦 日常の組合活動のなかでも、団体交渉に誠実に対応させる追求が必要です。不当な対応には、電話や口頭でのやり取りだけでなく、文書で具体的な資料提示を求め、要求を明確に、日付を明記して繰り返し団体交渉を求めることが、後に証拠にもなります。
森 組合員差別をする不利益取扱いも評価制度を使い巧妙になっています。加えて、団交を引き延ばすことによって不利益が生じる場合も不誠実団交と一緒に申し立てするといいと思います。支配介入も、ビラ配布禁止や組合員のみを処分するなどが典型例ですが、団交拒否や不誠実団交に「支配介入」の意思があると救済内容を広げて申立てれば勝機も広がると思います。
裁判より柔軟な解決力
三浦 裁判は「地位の確認」など限定的ですが、委員会は「原職復帰命令」「権限ある者の出席命令」「掲示板貸与命令」といった柔軟な命令が可能です。より現場に即した解決を図れるのが特徴です。委員会は三者構成で、命令の判定権限は公益委員がもっていますが、労使の参与委員がそれそれの立場で関与できます。
森 和解においても、救済申立て以上の成果を得ることがあります。例えば申立ては「不誠実団交」についてだったのに、和解で「今後の毎年の賃上げ」「最低○カ月ボーナス保障」などが盛り込まれる場合があります。委員会が労使関係改善に資すると組合の主張を理解すれば、積極的に和解案を提示するのです。そういう使い方は知られていないので、ぜひ知ってほしいことですね。

労働委員会の問題点-活用してより使いやすい制度に
三浦 いま、集団的労使関係の形骸化、労働組合の弱体化をねらう動きがあるなかで、労働者の団結権、労働組合の団体交渉権を強化するために委員会の活用がいっそう重要です。
森 過半数代表制を理由に労働組合との労働協約を全面破棄する事例が増えています。しかし、過半数代表には資料を出させる権限も、団体交渉を継続させる力もありません。労働組合でなければ勝ち取れない改善は多いのです。
三浦 全労連加盟組合でも委員会を使っているところは限られ、全体としても集団的労使関係の事件は減少傾向にあります。労働者の団結を擁護する制度が先細りしてしまう懸念を持っています。労働組合として積極的に活用していくことの重要性と、「使いにくい制度なら改善させる」という運動が必要です。
森 制度の使いにくさの点をいくつか指摘すると、労働委員会の初審、再審、さらに行政訴訟で地裁・高裁・最高裁と実質5審制になって時間がかかるようになりました。ただし、初審命令は行政命令なので、不服申立てをしても本来は従わなければなりません。しかし、その点が曖昧になっているため使用者側が命令に従わず長期化するので使いにくい。
三浦 初審で救済命令を勝ち取っても使用者側が再審査を申立て、団交拒否や不利益取扱いなど不当労働行為の解決に数年かかることもあります。再審申立てによっても初審命令の効力は停止しませんが、履行勧告に強制力がなく、再審査中の初審命令の実効性が確保されないことも問題です。
森 さらに、制度の致命的欠陥の一つは除斥期間です。不当労働行為事件の時効がわずか1年(民事請求権は3年)しかありません。労使関係は継続性を持つものですから、本来は時効が成立すべきではありません。実際に、経営者を説得しようと努力するうちに、気付けば1年が経過してしまうことも多い。こうした欠陥を踏まえても「どう活用するか」を考える必要があるのです。

組合の信頼と自信を取り戻す-職場活動との両輪で活用を
三浦 委員会の命令だけで要求実現や、組織拡大が進むわけではありません。いい命令が出ても改善に進まない事例もあります。「対話と学びあい」を通じた職場活動の強化と労働委員会の活用を「両輪」で進めることが必要です。
森 職場の運動とあわせて申立てしながら反撃できる点で、裁判とは異なる特色があります。もちろんこれは労働組合にとって強力な武器ですので使わない手はありません。
三浦 10月のレバカレでも「使ってみよう!労働委員会」分科会(11日・分科会B)を開催し、経験や課題を交流します。使いやすく役立つ労働委員会に改善していくのは、労働者・労働組合自身です。労働者は使用者と対等ではないからこそ、団結して交渉する権利が保障されています。団結を擁護する制度も活用し、対話と学びあいを広げて、要求を前進させましょう。
森 組織対象を広げ、多様な人を迎え入れる工夫も必要です。柔軟な使い方を研究し組織拡大につなげましょう。事例交流も重要で、会社名や金額を出せなくても概要を共有すれば学べます。制度を活用すれば組合の信頼と自信を取り戻し、現場の力になります。
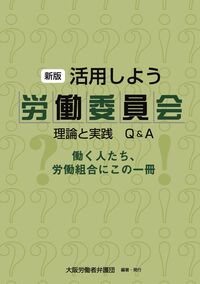
書籍紹介
労働委員会の活用のための手引書
『新版 活用しよう 労働委員会 理論と実践Q&A』
大阪労働者弁護団編著・発行
(全労連新聞590号 2025年9月15日発行)
- 女性部 (7)
- ぜんろうれんラジオ (14)
- 国際連帯 (18)
- 全労連新聞 (26)
- 月刊全労連 (50)
- 事務局長談話 (16)
- 対話と学びあいスクール (3)
- わくわく講座 (1)
- ゆにきゃん (8)
- 調査・報告 (11)
- 宣伝物 (46)
- 春闘 (83)
- 秋年末闘争 (23)
- メディア掲載 (12)
- ストライキ (11)
- 被災地支援 (9)
- 署名 (11)
- 動画 (16)
- 大会記録 (1)
- 集会・学習会 (54)
- 賃金・最低賃金 (68)
- 労働法制 (56)
- 憲法・平和 (87)
- 社会保障 (63)
- くらし (83)
- 選挙 (31)
- 学習・教育 (8)
- 非正規労働者 (49)
- 青年 (33)
- 女性 (37)
- 原発・気候危機 (3)
- ジェンダー平等 (101)
- 非正規センター (6)
- 国民大運動 (15)
- レバカレ (59)
- 対話と学びあい (58)