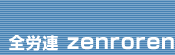|
概 観
スペインでは、2000年総選挙でも保守・新自由主義の国民党が勝利し、1996年以来、同党の政権が続いている(アスナール首相)。同政権は米英のイラク戦争を支持し、派兵もしている。経済指標では、全体としてほぼ前年と同じである。失業率はEUの他の国と比べては、依然として高いが、減少を続けている。名目賃金上昇率は前年3.9%より高い。
労働協約上の年労働時間(2002年)は1756.63時間で、2000年1761.3時間、2001年1760.1時間と比べ、短縮傾向が続いている。スペインは、1990年代末に、自治州の法制による週35時間制の導入が進んだことで知られ、2001年末現在で、140万人が週35時間制協約の適用化にあったが、2002年以降、この傾向は鈍化したと見られている。
| 2003年の指標 |
| 経済(GDP)成長率 |
2.3%
|
| 消費者物価上昇率 |
3.1%
|
| 失業率 |
11.3%
|
| 賃金(名目)上昇率 |
4.2%
|
| 財政赤字の対GDP比率 |
△0.0%
|
| 累積債務の対GDP比率 |
△51.3%
|
|
「欧州委員会経済予測」2003年
秋版による。 |
■2003年の主なたたかい・できごと
- 1月3日 政労使が労働災害予防の強化で合意。発生率を下げるための措置として、発生率に応じた労災保険料率の導入などを決めた。
- 1月30日 全国レベルの労使が、前年に続き、2003年賃上げ抑制ガイドラインで合意。
- 2月 政府が、反対世論に押されて、年金算定方式の変更を含む社会保障制度改革に関する議論を、2004年まで延期。
- 2月13日 多国籍自動車部品メーカー・バレオがサン・エステベス・デ・セスロビラの工場閉鎖を発表。労組との間で、256人の失職に関する退職金、早期年金入り、転職保障などで合意。
- 2〜3月 2大労連(CC.OO=労働者委員会連合、UGT=労働者総連合)が3月8日の国際婦人デーに向けて、女性の地位向上と家族政策の改善で一連の提案・要求を共同宣言として発表。
- 3月26日、4月10日 労働組合が政府のイラク戦争支持に反対してストライキ。
- 2月初旬 フランスのタイヤ・メーカー、ミシュランが向こう3年間にスペインで1300人の労働者を削減すると発表。
- 2月下旬 カタロニア高等裁判所が日産自動車の2002〜2003年労働協約に含まれる二重賃金基準(新規採用者の賃金を現職労働者より引下げ)を無効と判決(別掲本文「日産スペインの差別的賃金条項に無効判決」参照)。
- 4月25日 政府が雇用促進のためとして、一連の企業負担軽減措置を発表。
- 6月 固定電話企業テレフォニカ・デ・エスパーニャが労働組合との交渉中に、経営難を理由に約11%の人員削減計画を発表。
- 6月30日 アリカンテ裁判所がバレンシアにある繊維印刷企業ARDYSTILで1990年代に起きた職業病・健康障害(死者6人を含む)に関する裁判で、会社の責任(責任者に6年の禁固刑)と政府の監督責任(責任者に6ヵ月の禁固刑)を明確に認めた判決を下した。
- 9月 テレビ会社アンテナ3が労働者約4分の1を削減する手続きに入ると発表。労働組合がストライキで抗議。
- 9月 自動車メーカーSEATで土曜労働拡大(年間10日増)の事業所協定締結。
- 8月22日 石油精製企業REPSOL-YPF(所在地プエルトジャーノ)で起きた事故による重大災害(8人死亡、数人が重傷)に関して、下請け企業労働者が抗議スト。
- 12月 2大労連(CC.OO、UGT)が、スペインの最低賃金(SMI)はEU加盟国で下から2番目という低さを克服するためとして、月526ユーロを同660ユーロに引き上げることを要求(別掲本文「2大労連が最低賃金の25%引上げを要求」参照)。
■日産スペインの差別的賃金条項に無効判決
過去7〜8年の間に、スペインでは新規採用者と既存の労働者とで別々の賃金基準(新採用者が10〜30%低い)を適用する二重基準を含む一連の労働協約が、主に大企業で結ばれ、労働組合との間で紛争が起こっていた。なかでも日産グループの労働協約がとくに多くの問題を含んでいた。
日産グループの2002〜2003年労働協約は同じ職種で同じ仕事をする場合、新採用者と既存者では、前者の賃金が低くなる内容だった。その仕組み(やり方)は、ボーナス年2回全員支給を廃止し、その上で、それと同額を既存労働者には個別に保障し、新採者には支給しないというものだった(しかも、そのことは労働協約に明文化されていない)。協約には、経営状況が回復した場合の旧制度への復活や有期雇用者の無期限雇用への転換など代替措置も規定されていなかった(旧協約には、無期限雇用での採用は有期雇用者から、との規定があった)。したがって、2002年6月26日以降採用の労働者は、同等の既存の労働者と比べ年額平均で17%少ない賃金を無期限に受け取る契約を結ぶことになっていた。
労働者委員会連合(CC.OO)と労働総同盟(CGT)はこの条項を理由に同労働協約の調印を拒否したが、日産の労働者代表委員会の多数を占めるUGT(労働者総連合)と日産グループ独立労組が調印したため、協約は有効(発効)となった。そして、労働者委員会連合(CC.OO)が提訴に踏み切り、2003年2月下旬、カタロニア高等裁判所が同条項の無効を判決した(協約全体の無効ではない)。
日産側はこの判決を受けた当初、労働協約に定められた2003年分の賃上げを全労働者2400人に対して凍結するという対応に出たが、CC.OOが労働基準監督署に訴えたため、労働協約の規定を尊重することに改めざるをえなかった。しかし、高裁判決は受け入れず上告するとの対応を発表した。
■2大労連が最低賃金の25%引上げを要求
|
全国一律最低賃金の国際比較
|
|
(2003年月額、ユーロ)
|
|
国 名
|
月 額
|
スペイン=100とした指数 |
| ルクセンブルク |
1,369
|
260
|
| オランダ |
1,249
|
237
|
| ベルギー |
1,163
|
221
|
| フランス |
1,154
|
219
|
| イギリス |
1,105
|
210
|
| アイルランド |
1,073
|
204
|
| アメリカ |
877
|
142
|
| スペイン |
526
|
100
|
| ポルトガル |
416
|
79
|
|
|
資料出所:EU統計局
|
2大労連(CC.OO、UGT)は12月 、スペインの全国最低賃金制(SMI)はEU加盟国で下から2番目(別表参照)、平均賃金の40%に過ぎないという低さにあるとして、政府に対して、月526ユーロを同660ユーロに引き上げることを要求した。スペインの最低賃金は効果的な労働協約の適用下に含まれない労働者への最低保障を目的としており、約80万人の労働者が直接に、150万人の労働者が間接的にSMIの影響を受ける。SMIはまた、失業手当、賃金保障基金から支給される倒産企業労働者への保障、社会扶助給付などにも連動している。独立専門家委員会も全国の平均賃金の68%に引き上げるよう勧告している。(宮前忠夫)
|